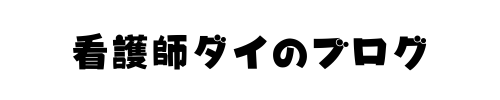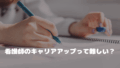はじめに
こんにちは!看護師のダイです。
「看護師って毎日忙しそうだけど、いつ勉強してるの?」
「分からないことがあっても、正直そのままにしちゃう…」
そんな声、よく聞きます。
かくいう私も新人の頃は、分からないことが山のようにあって、帰宅後はぐったり。「明日聞こう」「調べよう」と思っても、つい先延ばしにしてしまっていました。
でもその“放置”が続くと、自信が持てなくなるし、患者さんにも迷惑をかけるかもしれないですよね。
だからこそ今回は、「看護師はいつ勉強しているのか」、そして「分からないことを放置しないための勉強法」について、私なりの方法を教えます!
看護師が勉強するタイミングっていつ?

まず、リアルな話から。
看護師が勉強に充てられる時間って、「スキマ時間」が中心ですよね。
日頃の疲れを取りたい休日を丸1日使うなんて現実的じゃありません。
通勤時や帰宅後
公共交通機関で通勤している人はその時間を利用しましょう。
あとは帰宅して夕食後や寝る前に10分だけ調べ物。
無理に1時間とか気合を入れなくてOK!短時間の積み重ねが大事なんです。
勤務中の「合間」
ちょっとした休憩時間に、気になった薬剤や処置をスマホでサクッと検索。
最近は病棟に医療情報アプリが導入されているところも多いので、活用しやすいですね。
僕は勤務中分からないことがあったら昼休憩の時にYouTubeで検索して動画で勉強しています!
休日の午前中に
仕事の日は勉強なんてできない!という人は休日の午前中なんてどうでしょうか。
早起きすることで1日を長く感じることができますし個人的にはとてもおすすめです。
頭が冴えている朝に、分からなかったことをノートにまとめたり、解剖生理を復習したり。
休日の全てを勉強に使う必要はありません。午後はリフレッシュの時間にしましょう。
分からないことを放置しないための工夫

「あとで調べよう」と思っても、人はすぐ忘れてしまうもの。
なので、僕がやっている具体的な方法をご紹介します。
気になることをメモしておく
スマホのメモアプリや小さなメモ帳でOK。
僕は単語だけをメモすると後から見たときに何を調べたいのか分からなくなっちゃうんです(笑)
「ドパミンとノルアドレナリン何が違う?」のように疑問をその場でメモするのがおすすめです。
メモしたことは24時間以内に調べる
「明日やろうはバカヤロウ」なんて言うように、明日に回すと「一生やらない」になりがち。
帰宅後に1個でも調べて理解すると達成感があります。
また、記憶は定着するまで時間がかかります。
調べたらその答えも一緒にメモ帳に追記しておくといいでしょう。
自分専用の看護ノートを作る
分かったこと・覚えておきたいことを一冊にまとめておくと、次に同じ場面に出会ったときにすぐ見返せます。
看護の知識だけでなく難しい業務内容などもまとめておくといいでしょう。
勤務前に5分読み返すだけでも違いますよ。
さいごに

皆さん、これだけは覚えておいてください。
勉強=頑張るじゃなくていいんです。
「ちゃんとしなきゃ」と思いすぎると、疲れてしまいます。
でも、患者さんにとって私たちは“医療者”。
だからこそ、少しずつでも知識をアップデートしていくことが、自分の安心にもつながるんです。
そして、分からないことをそのままにせず「今のうちに調べてみよう」と思えることが、プロとしての第一歩だと思います。
看護師は“勉強が終わらない仕事”とも言われますが、それは決して悪いことじゃありません。
知識が増えれば増えるほど、患者さんの対応にも自信が持てて、看護がもっと面白くなります。
「完璧じゃなくていい。気づいたときに、ちょっとだけやってみる」
そんな気持ちで、これからも一緒に学んでいきましょうね。
あなたの明日の看護が、少しでも楽になりますように。